AIR FORCE 1 40TH
Index of the Message
Vol.01
The New
Photograph by Shunsuke Shiga
40年の歴史をディテールに詰め込んだ
特別な2022年バージョン
40周年を迎えたAIR FORCE1のアニーバーサリーエディション。その細部を覗いてみると、さまざまな時代のディテールにフォーカスしているのがわかる。まず、大きな特徴はボックスで、今回は2000年代初期に使われたオレンジ×ブラウン製をカムバック。シューズ全体のデザインもその時代をある程度ベースに作られている。シュータンに縫い付けられたタグは、ナイキロゴの下部にある「AIR FORCE 1」の文字を筆記体の「Anniversary
Edition」に変更。光沢糸でさりげなくリュクスに仕上げている。マニアが唸るポイントは、アイステイのつま先側に施された小さなスウッシュだ。これは現在には存在しないディテールで、ちょうどオレンジボックス初期である2000年頃のモデルには刺繍の跡が残っている。余談だが、Supremeがレギュラー展開している白と黒のAIR
FORCE1にはこのディテールが採用されている。そしてトゥボックス全体をみると、現行よりも丸みがおさえられている。補強部の厚みも薄く、輪郭はシャープ。これもまた、90年代後期〜2000年代の名残だろう。ヒールは当時を再現、ではないものの、スウッシュのないNIKE AIRのロゴが90年代以来戻ってきた。当時はプリントで、経年劣化とともに掠れて消えかかっているものが多いことから、刺繍が選ばれたのか。このディテールは、2020年に80年代のディテールを踏襲した通称 “ラベル
メーカー パック” に使われ、ヴィンテージ好きの間で密かに話題になったものだ。
最後に、映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』をご存知だろか。エア
ジョーダンのCMを手がけて時の人となったスパイク・リーが監督した、人種差別やNYの貧困区域を取り上げたポリティカルなムービー。劇中では、主人公のバギン・アウトが、歯ブラシでシューズの汚れを落とすシーンがあった。本作で付属する歯ブラシにも、白は手入れしてでもキープすべき、というカルチャー的なマインドを読み取ることができる。こうしてみると、フックアップしたディテールに年代の統一はないものの、この普遍的なベーシックにも細かな変遷があったことを知ることができる。2022年バージョンは偉大なヒストリアンである。
AIR FORCE 1 40TH
Index of the Message
Vol.02
Deubre
リュクスを得るカスタムカルチャーは
デュブレの存在意義を高め続けた
そこに大きなドラマが介在しているかと問われれば、首を大きく縦に振ることはないものの、AIR FORCE1にとって重要なディテールの一つにデュブレがある。このパーツは社内のフットウェアデザイナーのデイモン・クレッグが考案したと言われる。1994年に靴紐につけるタグについてプレゼンテーションする際、それを指す最適なワードを探しているうちにこの言葉に辿り着いたとか。おそらく1996年頃のモデルから一部のAIR FORCE
1にデュブレが標準装備されている。初期は、オーバル型で少しくすんだシルバーの質感だったが、2002年には20周年を記念してアップデートされている。2006年のカタログにはNIKE自らこの言葉を使うようになり、2007年の25周年には、よりアクセサリーのようなプレート状に進化した。僕がデュブレという言葉を知ることなしに小さな変化に気づいたのは、おそらく2000年頃。AIR FORCE 1の「Puerto Rico」や「West
indies」などの(当時は希少な)限定モデルにプラスチックのデュブレがついていて、何か特別な意味を感じ取っていた。20代の頃、週末にNYへ行く度によく遊びに行っていたのが、ミッドタウンの問屋街だった。47thストリートからジュエリー専門店が並んでいて(ウィッグ系も多い)、そこにはいわゆるゴールドやダイヤモンドなどのいわゆる「本物」から、メッキ系のアクセサリー店までたくさんあった。東京で言うところの上野〜御徒町だろう。そのメッキ系のアクセサリー店には、黒人のラッパーたちが首からぶら下げている鎖のようなゴールドのチェーンや、スワロフスキーのようなものでデコレーションされた遊び半分のネックレスやベルトのバックルがびっしりと並んでいた。半日も待てばオリジナルのバックルが30ドルくらいで作れたので、日本の友人のお土産に名前入りのプレートを作って持って帰ったものだ。そこには派手に象られた金銀のデュブレがいつの間にかあって、ヒップホップ系に強い並行輸入店などは、このノーブランド品を買い付けていたと思う。アメリカの成功した黒人ラッパーが成功の証に日用品をラグジュアリーにカスタムする感覚が、日本のストリートのアイデアの基盤になって久しい。例えば車、ガラケー、当時はキラキラとしたフリスク専用のケースなどもあった。90年代にアウトドアブーツのように重厚で丈夫だったことでN.Y.のストリートに愛されたAIR
FORCE1 も同じように成功の証で、デュブレは価値を上げる重要なパーツだった。薄底のDUNKにはなくて、厚底のAIR FORCE1 に付属する理由はそこだろう。
AIR FORCE 1 40TH
Index of the Message
Vol.03
Mid
Photograph by Shunsuke Shiga
世界中を巻き込んだ2000年代のムーブメント前夜、
ミッドカットのデザイン実験が行われていた
スニーカー、いやスポーツシューズの世界において、最初からミッドカットが作られることはない。「ミッド=中間」という意味だけに、その両端があってこそ生まれるのがミッド。ハイとロー、それぞれの高まる需要を分散させるかのように「じゃあミッドも作るか」という”おまけ”というか、遊び心的な存在ではないだろうか。それゆえスニーカーにミッドカットが定着したモデルは知る限りほとんどない。AIR FORCE 1と横並びで扱われるようなAIR JORDAN
1もミッドは後発で、立ち位置は正直微妙だし、DUNKに至っては2003年頃にミッドがひととき出た以降は、SBに系譜が委ねられてしまった。本流はあくまでハイとローで、ミッドにはNIKEも本気を出してこない。そんな印象すら感じている。
しかしながらマニアの視点からいえば、AIR FORCE 1に限っていうと、モデル自体の普及にミッドが大きく貢献した。ローの登場から遅れること11年、1994年にミッドは登場した。90年代に入ると、AIR FORCE
1のフィールドは屋内コートから屋外コート、広義的にストリートに移っていて、80年代の様式美を90年代にフィットさせるかのように誕生したのがミッドだった。この前述した遊び心的な部分を、時代にうまくコミットさせていたと思う。配色のレイアウト、マテリアル、ジュエルスウッシュ、90年代中頃から生まれたたくさんのバリエーションは、どれもミッドに使われることが多かった。良い意味で、本流でないものに要素を盛り付け、遊んでいたのではないかと考察する。
僕の知る限り、世界で一番AIR FORCE 1を所有しているコレクターであり、地元の先輩でもある武井祐介さんは、中でも1997年に発売されたミッドカットの通称「INDEPENDENCE DAY」が、40年に及ぶAIR FORCE
1の歴史において大きなターニングポイントだったという。補強部の配色を切り替えるアイデアは、95年頃からミッドで始まっていて、ローカットに採用されるにはまだ5年ほど先のこととなる。武井さんは「新しいものを試すなら、新しいミッドで、という動きを当時から感じていました。素材もディテールも、基本的にミッドで導入する動きだったと思います」と所見を述べる。97年は、まだランニングシューズを中心としたいわゆる「ハイテク」の全盛期だった。そうした波にミッドを巻き込もうとNIKEは考えたのか。「ジェエルスウッシュ、クリアソール、メタリック素材、そしてデュブレもすべて付いている。INDEPENDENCE
DAYは、クラシックなAIR FORCE 1が当時のハイテクに負けないデザインを表現できることを示していた」と付け加える。
思い返せば僕も初めて購入したAIR FORCE 1はミッドだった。98年以降はミッドばかりがヒップホップ系の並行輸入ショップにたくさん並んでいて、DJ
MUROさんのサベージ、マンハッタンレコードのクロージング専門店、グロウアラウンド。これら宇田川町界隈の名店にはミッドが占めていたと記憶する。当時はほとんどがジュエルスウッシュ(ジェルスウッシュの方が一般的ではなかったろうか、僕のコミュニティが間違っていただけか……)で、シューレースは丸紐がわりとスタンダード(それでも平紐の方が人気だったと思うが……)。そしてフットアクション別注がとにかく良色ばかりで、ジョージタウンやAIR JORDAN
1をイメージした黒赤とか黒青などもあった。98年には「FLAX」の名で最初の”ウィート”カラーがミッドで発売されている。こうしたカルチャーを落とし込む作業は、既にミッドで実験的にトライされていて、その経験が2000年代、爆発的なローカットのムーブメントへと流れていったのだ。
AIR FORCE 1 40TH
Index of the Message
Vol.04
WMNS
Photograph by Shunsuke Shiga
CO.JPの大きなムーブメントを迎える前夜、
ウィメンズのインラインが種を蒔いていた
Interview with Katsushige Kamamoto[SKIT]
肌感では、日本におけるAIR FORCE
1の人気規模は、日本のヒップホップシーンのメジャー化と比例している。2000年前後になると、それまでは限られたカルチャーの枠内だったヒップホップがオリコンチャートにもランクインするようになった。先人が築き上げてきた基盤を受け継ぎ、万人にとって心地よさを伴いながら発展させたアーティストが続々と登場しては成功を収めていく。そうした変遷を当時20歳前後の立場でリアルに体感していた僕とSKITの鎌本さんは、同い年という共通頃もあってか視線は近く、盛り上がる点は多い。
「90年代のAIR FORCE 1は、海外のアーティストに限った話ではなく日本でも成功者が履いているシューズでした。DJ MUROさんのような90sの先駆者に憧れる人と、その人に憧れる人。その次……といった成功者の連鎖がカルチャーを作っていました」と鎌本さんは回顧する。そして2000年を過ぎた頃から、その規模が一気に膨れ上がった。ちょうど国内正規でウィメンズのAIR FORCE
1が9000円の定価で発売されるようになった頃。「白ベースにジュエルスウッシュのローカットとか。メンズより一足早く、ナイキジャパンがウィメンズでAIR FORCE 1をちゃんと展開し始めたんです。当時、裏原宿の流れでスニーカーをしっかりと追っている人たちは、SEISMICやKUKINI、Prestoといったハイテクを追っていて、その流れを追っていなかった。ヒップホップから形成されていった、似て非なるストリートスタイルがこれらのAIR FORCE
1に注目していて、数少ない大きなサイズは既にインラインでもプレ値がつき始めていたんです」。
atmosがジョージタウンカラーで別注し、CO.JPが急速に花を咲かせたのは2001年だから、その前年に種はすでに芽吹いていた。「白×パープルとか、白に履き口だけピンクみたいなローカットの海外限定も大きなサイズが人気で、よく買い付けていました。男性がウィメンズのスニーカーを買うと、店員から訝しげな目で見られていた時代だからよく覚えています」。
限定モデルであったわけではないが、鋭い嗅覚をもったバイヤーは常に条件の良いスペースをいつも探っていて、メーカーの意図せぬ土壌にムーブメントの種は蒔かれてきた。「PV」、「レコードジャケット」、そして「じつは数が少ないウィメンズ」が目の付け所だった。ネットがそこまで普及せず、情報が伝達していくスピードにいくつかのレイヤーがあった時代だからこそ、AIR FORCE 1はストリートという大きな波に乗れたのかもしれない。
僕が唯一、ウィメンズで個人的に思い出深い“バレンタイン”のAIR FORCE 1も、鎌本さんが仕掛け人だったようだ。「2003年に『グッドラック』という木村拓哉さん主演の月9ドラマがあって、そのシューズの衣装協力をしていました。そこで一瞬だけ、バレンタイン限定のAIR FORCE
1を履くシーンがあるのですが、かなりカメラが足元にフォーカスされてたんです。その日まではとくに人気があったわけではなかったのに、翌日から店舗に3台あった電話が鳴り止まなかった。バレンタインもウィメンズだったから、メンズサイズが少なくて。60〜70足くらい仕入れただけだったので、すぐに売り切れてしまいました」。僕もそのシーンをちょうど家でテレビを見ていて、映った瞬間に留学していたフィラデルフィアの友人に国際電話をかけ、買えるだけ買ってとお願いしたのは懐かしい思い出(送ってもらったのは8足程度だが、送料と友人への謝礼でとくに儲けはなかったのもまた思い出)。そうしたモデルが話題になるのも、日本が世界でもっとも文化的に先進したマーケットだったからだろう。
AIR FORCE 1 40TH
Index of the Message
Vol.05
Culture
Photograph by Shunsuke Shiga
テン年代のスニーカーカルチャーを変えたのは
黒の認識、トリプルブラックの浸透にあった。
2010年代にAIR FORCE
1が世の中のスタンダードになった功績は、ピュアホワイトよりもトリプルブラックの方が大きい。2000年代、その普遍性にゆえに見逃され続けてきたオールブラックは、いつしか多くの愛情が注がれるようになり、もっともクールなカラーとなった。アッパーもソールもすべて黒は、汚れが目立たない。だからこそ、何足も買い換えない。つまりオールホワイトが汚れるたびに買い換えるのは成功の象徴であるのに対し、黒は貧乏人のためのカラーとも言われた。かつては夜に溶け込む泥棒の色とも揶揄されたこともある。
もう20年も前になるが、かつてatmosの本明社長に「アメリカでは地面に溶け込む色は売れないよ」と言われたことがある。つまりグレーや黒、芝の上を想定すれば迷彩やグリーンか。こういった目立たないスニーカーは売れにくい、と聞いて「なるほど」と思ったものだ。
相変わらず真っ白は売れ続けているものの、時代も変わった。アメリカの成功者は、ゲトーから這い上がったラッパーよりも、シリコンバレーの億万長者にフォーカスが当たっている。彼らは派手であることを嫌い、服装も質素だ。シューズはスキニーのボトムスと同化するような黒いシューズを好む。ちなみに、かつてNIKEの元CEO、マーク・パーカーも好きなシューズの色は「トリプルブラック」と笑って話していた。つまり「IYKYK(=If you know, you
know)」なカラーというわけだ。
2012年頃、日本でも大きなスニーカーブームが訪れはじめた。僕がその流れを原宿界隈で感じたのは、それまで革靴がメインだったデザイナーやクリエイターが、真っ黒のスニーカーを履くようになったことだ。スニーカーカルチャーや裏原宿の文化に割としっかり浸かっていた人にとって(僕もその一人でもあるが)、黒ソールがどうしても慣れない。当時は、フライニットやAIR MAX
2013など、最新のハイテク機種に真っ黒なカラーがラインナップされるようになり、それまでのオールデンなどの革靴から、違和感なく足元を軽くしたいというマインドの変化から、こうしたオールブラックのスニーカーが重宝されるようになった。そしてしばらくすると、周りは真っ黒のAIR FORCE 1をこぞって履くようになっていた。AIR FORCE 1のレザーの質感は、スニーカーの中でも革靴の部類であり、欲を言えばシルバーのデュブレを外し、黒であることを主張するのだ。その後、AIR
HUARACHEやAIR MAX PLUSなど、時代を彩ってきたスニーカーも、OGよりブラックがヒートするなど、いつの間にか真っ黒は、純粋に英訳されたオールブラックというワードから、いつしかトリプルブラックという一つの価値をもった言葉がつけられた。アグレシッブなツーリングを包み込んでしまう黒いソールは、A$AP ROCKYが履いたVLONEのAIR FORCE
1がハイプな世界に決定的な認知をもたらし、Supremeが定番的にトリプルブラックをリリースしている事実がスタンダードであることを証明させている。
ブラックフライデーの解釈が変わったことも影響しているのではないか、と個人的には考えている。Amazonではブラックフライデーの期間、黒いものだけを集めてセールにするなど、いつしかネガティブなイメージを払拭し、とくにサイバーの世界で黒は、いつしか黒字の象徴になっていった。こうした世の中の動きも、黒の価値観を変えたのではないか、と思っている。

















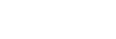




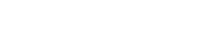










 NIKE AIR FORCE 1 MID '07
NIKE AIR FORCE 1 MID '07 NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07
NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 NIKE W AF1 SHADOW
NIKE W AF1 SHADOW NIKE AIR FORCE 1 '07
NIKE AIR FORCE 1 '07 NIKE AIR FORCE 1 '07 LX
NIKE AIR FORCE 1 '07 LX NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8
NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 LX
NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 LX  NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 LX
NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 LX NIKE WMNS AF1 LXX
NIKE WMNS AF1 LXX NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 MID LX
NIKE WMNS AIR FORCE 1 '07 MID LX NIKE AIR FORCE 1 '07 PRM
NIKE AIR FORCE 1 '07 PRM NIKE AIR FORCE 1 '07
NIKE AIR FORCE 1 '07